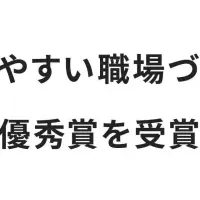

くら寿司が提案するSDGs学習プログラム「お寿司で学ぶSDGs」とは
くら寿司が提案するSDGs学習プログラム「お寿司で学ぶSDGs」とは
2025年11月13日、島根県宍道小学校にて「お寿司で学ぶSDGs」という特別な出張授業が行われます。このプログラムは、くら寿司株式会社と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが協力して実施するもので、未来を担う子どもたちが海洋環境や食品ロスについて学ぶことを目的としています。
プログラムの背景と目的
近年、私たちの生活に影響を与える海洋資源の減少や食品ロスの問題が深刻化しています。こうした課題を解決するため、子どもたちが「海の恵み」を意識し、未来へとつなげる行動を考えることが大切です。この授業では、SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」といったテーマに基づき、知識を深める内容となっています。
授業では、実際には隠岐諸島で行われた体験学習「隠岐めしと歴史 探険隊」の映像を通じて、地域の漁業の現状やそこに潜む課題を学びます。また、児童たちには「お寿司屋さん体験ゲーム」や「魚模型を使ったワークショップ」を通したインタラクティブな学びが用意されています。
授業内容の詳細
1. ### 隠岐めしと歴史 探険隊の動画上映
このセクションでは、海と日本プロジェクトinしまねが開催した体験学習の映像が上映され、子どもたちは隠岐の海の恵みとその文化的な背景を学びます。朝廷に献上された隠岐の魚の歴史や、地域の漁師から学んだシロイカの捌き方など、実際の体験を通じて得られた知識を深めます。
2. ### くら寿司の出張授業内容
この授業は3つのパートで構成されています。
- - 未来ではお寿司が食べられなくなる!?
- - お寿司屋さん体験をしよう!
- - 解決案を考えよう!
これらの活動を通して、子どもたちには自ら考え行動する力を引き出し、持続可能な社会の形成へつなげることを目指します。また、宍道小学校の他に松江市内の3校でも同様の授業が行われる予定です。
取材案内
授業内容の紹介に関連する商品も取材可能で、旬の海鮮丼やかにみそなど、島根県の新鮮な海の幸が使用されています。具体的な取材日時は、2025年11月13日(木)の11:00から12:00の間にくら寿司松江店で行われます。
終わりに
この取り組みは、次世代の子どもたちが海洋環境や持続可能な食文化について学ぶ良い機会です。くら寿司と海と日本プロジェクトのコラボレーションによって、より多くの子どもたちが「海の恵み」を意識し、これからの未来にどう繋げていくかを考えるきっかけとなることを期待しています。興味のある方は、ぜひ取材参加を検討してみてください。



関連リンク
サードペディア百科事典: 海と日本プロジェクト SDGs くら寿司
トピックス(その他)
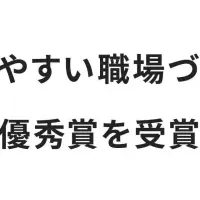
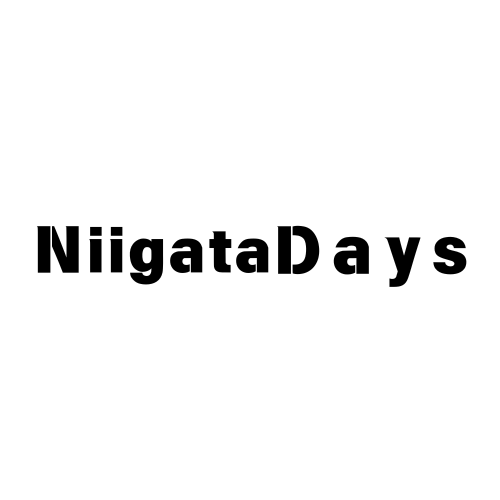

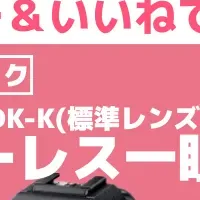


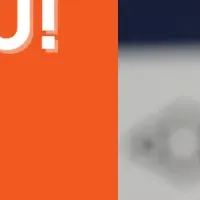
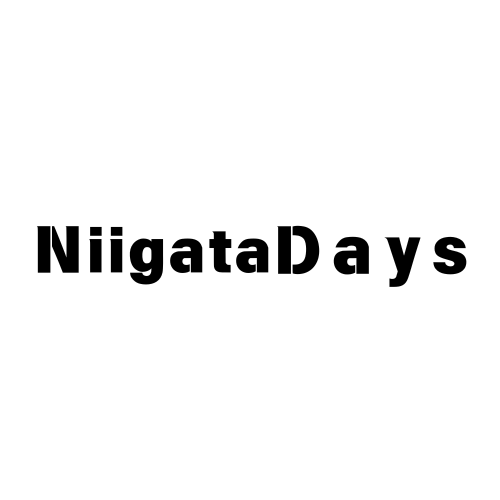


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。